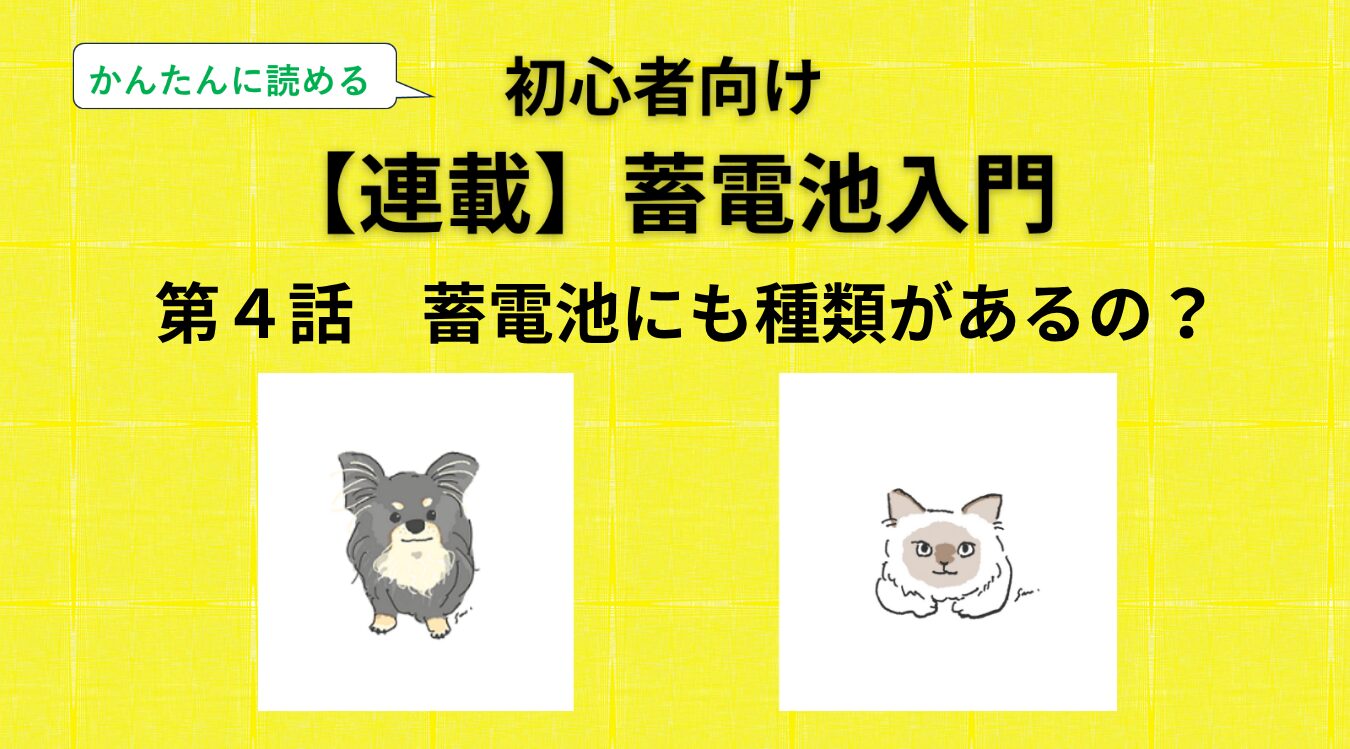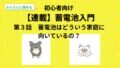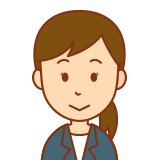
蓄電池の製品の違いって、貯められる電気の量の違いだけじゃないのね!?
どんな点を検討して選べばいいのかしら・・・。
機能面でみた4つ(=2×2)の種類
『全負荷型』にするか『特定負荷型』にするか

蓄電池っていろんな種類があるみたいだけど、違いって何?

まず一つに、機能面でみると、『全負荷型』と『特定負荷型』という種類があるよ。

少し難しくなってきたかも。名前からして、よく意味がわからニャいわ・・・

大丈夫!説明するワン。
『全負荷型』は、停電時に、家のすべての場所の電気が使えるわ。一般的な家電の100V(ボルト)電圧家電だけではなく、エアコンやIHクッキングヒーターなどの200V(ボルト)電圧家電も使用できるわ。

つまり、普段と同じように生活できるってことね。

そう!蓄電池にためた電気が残っている限りは・・・

じゃあ『特定負荷型』は?

停電時に、あらかじめ決めた家の特定の場所の電気だけしか使えないわ。そして200V(ボルト)電圧家電も使用できないの。

限られた家電だけを動かすのね。非常時に最低限の生活を維持する感じだわね。停電時は、冷蔵庫とスマホ充電くらいには使えそうね。

そうだね。「全負荷型」と比べると、費用は安いわ。
『ハイブリッド型』にするか『単機能型』にするか

もう一つ、『ハイブリッド型』と『単機能型』という分類もあるんだ。

ふむふむ。『ハイブリッド型』って?

『ハイブリッド型』は、太陽光発電のパワーコンディショナー(※)と蓄電池のパワーコンディショナーが「ハイブリッド」という名のとおり、1台に兼ね備えられた機器よ。
(※)パワーコンディショナーは、太陽光で発電した電気(直流)を家で使える電気(交流)に変換する機器です。

ふーん・・・

まあ、細かいことは置いといて。
『ハイブリッド型』の特徴をお話するね。
『ハイブリッド型』の特徴
👉電気のロスが単機能型より小さい。
👉停電時に、同時にたくさん電気を使える。
👉停電時に、自動で「自立運転」のモードに切り替わり、何も操作することなく蓄電池の電気が使えるようになる。
●単機能型と比べ、費用は高め。

じゃあ、『単機能型』の特徴って?

簡単にいうと、ハイブリッド型の逆ね。
『単機能型』の特徴
●電気のロスがハイブリッド型より大きい。
●停電時は、同時にたくさん電気を使うことはできない。
●停電時に、手動操作で「自立運転」のモードに切り替える必要がある。
👉ハイブリッド型と比べ、費用は安め。

『ハイブリッド型』の方が費用面以外ではいい点が多いけど、なにか決め手はあるのかニャ?

太陽光パネルと蓄電池を同じタイミングで導入するご家庭は、それぞれのパワーコンディショナーが1台に兼ね備えられた『ハイブリッド型』を選ぶことにムダがないわね。太陽光パネルの後から蓄電池を導入する場合は、もともとの太陽光発電のパワーコンディショナーがムダになってしまうけどね。
卒FIT(太陽光パネル設置後10年以上経過)のご家庭も、太陽光発電のパワーコンディショナーの寿命(一般的に約10年~15年)が近づいている状況だから、『ハイブリッド型』の蓄電池を導入することで、太陽光発電としてのパワーコンディショナーの交換もできたということになるので、『ハイブリッド型』にしてムダはないと言えるわ。

その2つのタイミングが、「蓄電池導入のいいタイミング」とも言えるかもね。

そうだワン。
<まとめ>機能面でみた種類

ということは、蓄電池は、「機能面」では、まず「全負荷型」か「特定負荷型」のどちらとするか、次に「ハイブリッド型」か「単機能型」のどちらとするか、ということを決めて、その組み合わせを考えればいいのね。

そのとおりだワン。
防災(停電)対策をしっかりやっていきたいのであれば、『全負荷型』かつ『ハイブリッド型』という組み合わせがベストだワン。停電時に電気の利用制約を一番受けなくて済むからね。

ところで、停電の時って、太陽光パネルだけだと、天気が良くてたくさん発電していたとしても、その場で同時に使える電気は限られてしまうの?

残念ながら、そのとおりなんだ。停電時は「自立運転モード」に切り替えるんだけど、同時に使える電気の消費量は限られてしまうんだ(1,500Wまで(※))。
でも『ハイブリッド型』の蓄電池を導入することで、停電時にも、太陽光で発電した電気を蓄電できるし、同時にたくさん電気を使うこともできるようになるんだ。
(※) 例えば、ドライヤーの消費電力は、1,200W程度と言われています。
物理的な面での違い

何かその他に違いってあるの?

物理的な面の違いかな。蓄電池製品の各部材が一つの大きな箱のようにまとまっている「一体型」なのか、それとも部材はまとまってはいないけど一つ一つの部材が小さくコンパクトである「分離型」なのか。

一体型はスッキリだけど存在感もあるかもね。

あとは、蓄電池本体を地面に置くタイプなのか、それとも壁掛けタイプなのか、といった違いもあるわ。

ニャるほど。家のスペースの制約とか、外観の印象とかで判断ね。家の脇にある程度のスペースがあれば、外の地面に置くタイプでも大丈夫かも、って感じで。
その他、便利機能

電気の使用状況や発電・蓄電状況が分かる室内モニターが付いているのか、スマフォで見るタイプなのか、その辺も製品によって違うワン。

室内モニターがリビングルームにあれば、家族団らんの時でも、発電量や電気の消費量が自然にリアルタイムで目に入って、家族みんなの節電意識の向上にもつながりそう!
スマフォで見るタイプのメリットは、外出している時でも気になる発電量や電気の消費量が見られるところね。

翌日の天気予報や、過去の発電や電気の消費量の実績に基づいて、最適な蓄電量を AI が予測して、夜間に電力会社から(安い)電気を買って蓄電池に充電する量を⾃動でコントロールしてくれる「気象連動 AI」モードは、毎日自分で何か判断や作業をしなくてもすべて自動で「最適」を判断して動いてくれる機能なので大変便利よ。

それはぜひお世話になりたい機能ね!
適切な蓄電容量は?

蓄電池にためられる電気の量も製品によって違うのかな?

そうだね。実はそれも重要なポイント!いわゆる「蓄電容量」ね。

たとえば、昼間に余る電気が1日10kWhなら、それに近い容量の蓄電池(10kWh程度)がちょうどいいってことね?

そう!10kWh余った電気があるなら、それをすべて蓄電池にためたいよね。少しでも、電力会社から買う高い電気を減らしたいわけだから。
まとめ

今日の話をまとめると、防災(停電)対策をどこまでしたいかによって、そのニーズにあった種類(機能)を選び、さらに余剰電力量に見合った蓄電容量の蓄電池を導入することで、蓄電池を効果的に使うことができて、暮らしの安心と節約の両方が手に入るってことね✨

そう。うまくまとめてくれてありがとう!
各ご家庭にピッタリの蓄電池を見つけてほしいわ。
\かんたん入力、無料で複数社からの見積り。蓄電池の一括見積りの代表的なサイトです(↓リンク)/
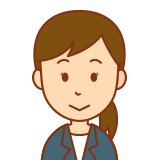
次回のテーマは、蓄電池の相場価格、についてです。